

編集者の仕事の魅力
唐澤俊介(2019年入社 新卒採用)
- 編集部門
- 編集・児童書
- 6年目


唐澤俊介(2019年入社 新卒採用)
「書籍編集者」と聞いて、皆さんはどんな仕事を想像しますか? 自分は正直、「著者からいただいた原稿のチェックをしたり、進行管理をしたりする人」といった程度の認識しか持っていませんでした。しかし、実際にやってみると、その仕事の幅広さに驚きました。まずは「企画作り」。これが始まりであると同時に、編集者の仕事のキモだと思っています。ここがしっかりしていないと良い本にはなりません。この本のウリはどこで、どんな人が買ってくれるのか、そして読んでくれるのかなど、説明を聞いた人が納得できるような根拠が必要です。
苦心して考えた企画が通ってからも終わりではありません。今度は書籍の中身をデザインしていきます。内容をどうするかはもちろんのこと、それをどう構成すれば、読者により伝わり、面白くなるのか。漫画を使うのがいいのか、イラストを入れたほうがいいのか。執筆や監修、イラスト、ブックデザインはどなたにお願いするのか。
それと並行して、どう売っていくのか、見せていくのかを考える必要もあります。どういったPR方法が効果的なのか。帯に載せるコピーをどうするか、目立つ表紙はどんなものか、書店ではどう見えるのか……などなど。書き出していくときりがありません。そのくらい編集者がやっている仕事、やるべき仕事は多岐にわたっています。
ここまで読んで、「編集者って大変。自分にはできない」と思った人がいたら、ちょっと待ってください。そんなことありません! 正直に言うと、自分が生活・文化編集部に異動してジュニア向けの出版物の担当になることを知った時、「児童書ほとんど読んだことないですけど、大丈夫っすか!?」と思いました。でも、何とかなっています(と自分では思っています)。自分自身の頭の中に漠然とあった企画の種を育てていき、本という形あるものにしていく経験は、編集者の醍醐味です。月並みな言い方ですが、強い好奇心があれば編集者の仕事はできると思います。
楽しいですよ、編集者。
(2024年12月執筆)


入社後、営業本部販売部書籍課で新書や選書、「TOEIC® TEST 特急 シリーズ」などを担当。3年目に朝日新聞社盛岡総局で一年間、記者として勤務。その後、週刊朝日、AERA dot.に配属される。2024年4月、生活・文化編集部に異動し、「実験対決」シリーズなどの児童書を担当している。

今日は朝イチで、著者と1時間の打ち合わせをしてから出社。

社屋にある書店に行って、新刊をチェック。自身の担当する書籍の参考にします。

お腹が空いたので社食へ。

原稿をチェック。誤字脱字はもちろんのこと、時には構成を変えるなどして、より魅力的な書籍にできるよう頭をひねります。

企画は編集者の仕事のキモ。練りに練った企画を同じ部署の人に提案します。

少し疲れたのでコーヒー片手に外で休憩。

ショート動画で書籍のPRも。カメラや照明などがセッティングされたスタジオは緊張します。

書籍の内容に間違いがないか、資料室で調べものをすることもあります。


業務部デスク箕輪政一
お仕事の醍醐味はなんですか?(唐澤)
業務部の仕事の醍醐味は、「本の製作に寄り添えること」です。(箕輪)
本の製作にあたり業務部が編集者に確認するべき項目は多岐にわたります。その本の大きさはどのくらいなのか。どんな種類の紙を使うのか。カバーに特殊加工はあるのか。オビは付けるのか。製本の仕方は上製なのか、並製なのか。本文は1C(モノクロ)なのか、4C(カラー)なのか……。
編集者から「こんな本をつくりたい」と相談されたら、まずは、製作にかかる費用がどの程度になるのかを試算したうえで、編集者に定価はいくらぐらいで販売したいのかを確認し、その費用と定価であれば、何部を販売できれば収支が合うのか、を検討します。編集者は、業務部が検討した収支などの結果を盛り込んだ企画書を手に、企画会議に臨みます。
本の企画書が無事に社内の企画会議を通り、発売日が決まったら、業務部はそこから逆算して本の製作全体の進行スケジュールを立て、その本の製作が完了するまで進行を管理します。特に重要なのは、校了に間に合うように管理すること(校了とは、印刷物の制作過程で最終的な校正確認が完了し、印刷に進むことが承認された状態です)。校了に間に合わなければ、本は出来上がりません。
本の大きさには、もっとも小さな朝日文庫からB4変判の『羽生結弦写真集 Tai』のような大きくて函入りのものもあります。
用紙は、どういう大きさの紙をつかえば効率的に作れるか、頭をなやまします。既定の用紙のサイズに対して無駄なく印刷をすれば、印刷費のコストダウンをはかることができるからです。
印刷方法や用紙の選択次第で、定価が大幅に変わり、結果、本の売り上げにも影響を与えます。なぜ、そのカタチになったのか。理由があるんです。
校了から発売までのスピードが重視される本もあります。たとえば『AERA増刊 甲子園』です。夏の全国高等学校野球選手権大会、地方の予選大会が終了し、甲子園球場での本大会が始まる数日間のうちに発売日を迎えたい。そのために、編集部、校閲担当者、印刷会社さんなどとは事前に綿密なスケジュール調整を行います。 また、売れ行きがよい本は、重版される部数も、回数も増えていき、その結果、使いたい用紙の調達が滞りそうになることがあります。この状況は、業務部にとっては、嬉しい悲鳴ではなく、ただの悲鳴に……。用紙の代理店の方、用紙のメーカーさんとの交渉を経て、「紙がない」という事態を全力で回避します。
一冊の本について、編集者のアイデアをカタチにして送り出すまで、寄り添い方が本によって様々なこと。その時間を味わえることが、業務部の仕事の醍醐味です。
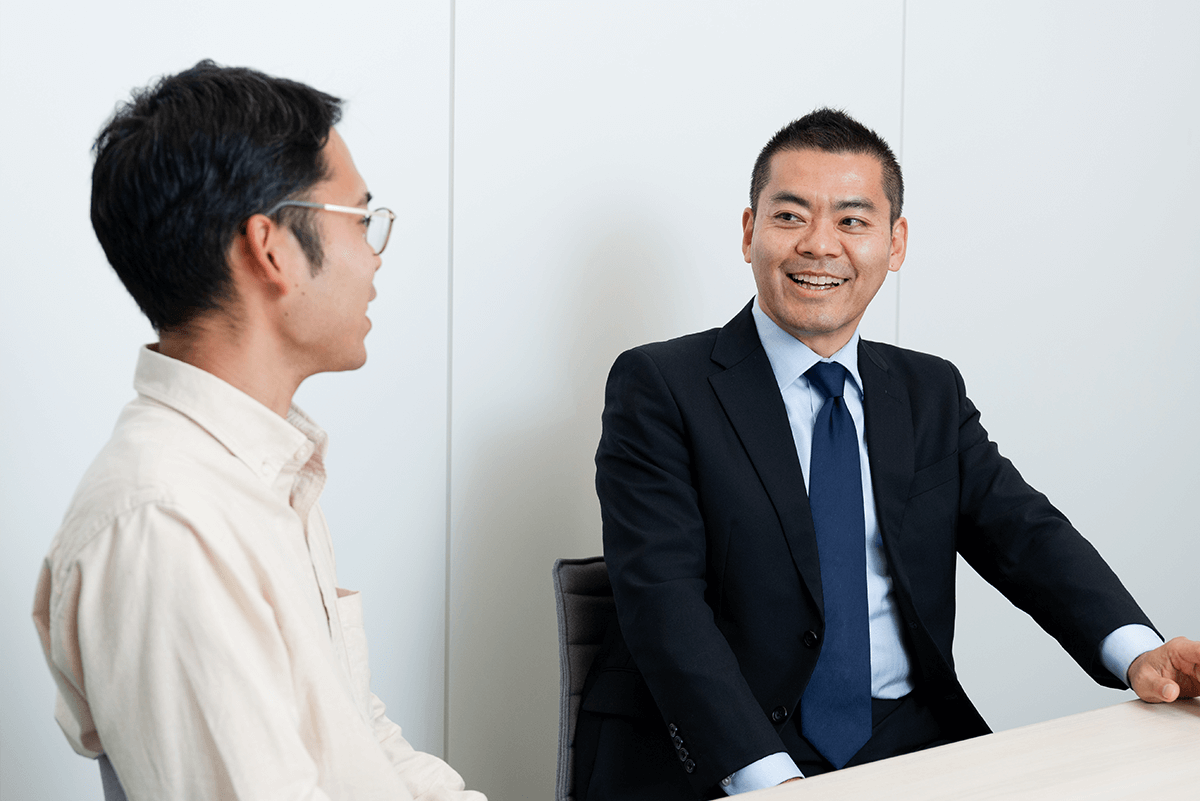
撮影:写真映像部 和仁貢介